2025.11.21
11月も後半に差し掛かり
秋の気配が冬に押され気味になってますが
みなさん、如何お過ごしでしょうか
おつかれさまです
伊丹のおくりびと、はやみんです♪
今日は満中陰法要のお話です。
満中陰法要の中でも
日程のお話です。
例えばスマホアプリに法事というアプリがあり

いろんなアプリがありますね♪
このアプリには
年忌表示と中陰表示の機能があり
命日を打ち込むと
中陰法要の日程早見表が表示できます。
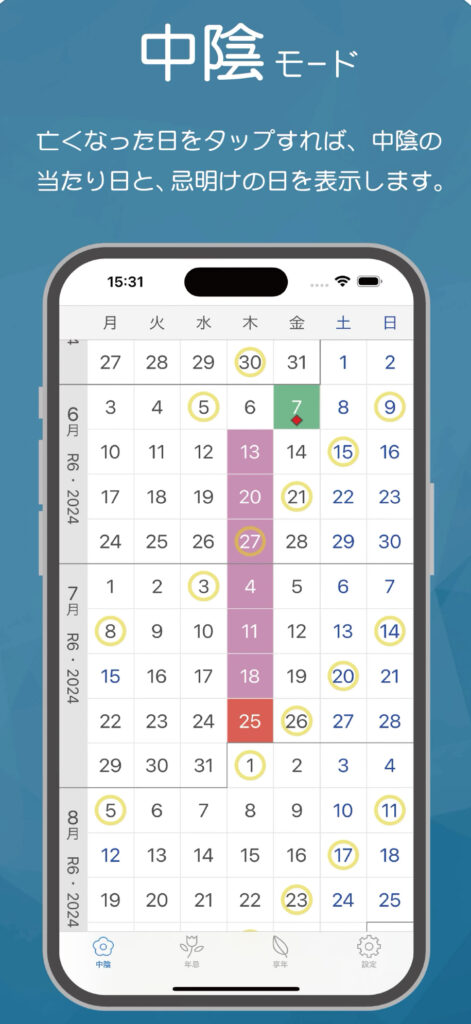
のですが、これは
命日を当日として数える関東式で
関西は関東より一日早い日程になります。
その理由は
昔々の大昔、物を数える時
基本的に「0(ゼロ)」は存在せず
全て一(いち)から数え始めていました。
紀元前5世紀頃のインドではすでに
ゼロの概念を体系的に使われてましたが
世界的に使われるようになったのは
7世紀になってからだというお話は
有名ですね♪
話を戻しまして、たとえば今日
現代の数え方で11月21日の7日後は28日なんですが
当日を1と数えると27日になります。
なので関東式では
21日が命日だと27日が初七日になります。
関西では初七日がその前日、
26日になるのですが
その理由はお通夜の概念です。
中陰の日程表にも「逮夜」と書いてあります
その昔、初七日以降の七日参り(中陰参り)毎に
前日のお通夜も営んでいたんですが
時代とともに省略化が進み
関東では七日参りの当日に
関西ではお通夜の日にお参りするようになりました。
ということで
関西では11月21日に亡くなった場合
初七日は11月26日になり
満中陰(四十九日)は
来年の1月7日になります。
中陰期間が年を跨ぐ場合は
四十九日を三十五日など繰り上げ法要にして
年内に収める方が多いです。
が
11月27日に亡くなると
三十五日が元旦になってしまい
前倒ししにしても年を跨いでしまいます
そんな時は本来の四十九日にすると
法要が1月15日になります。
関西では松の内が明けるですね♪
昔は松の内はお葬式も法要も避けて
松の内が明けてから改めて執り行っていたので
ちょうどいいかもしれないですね♪
以上、お正月にまつわる
中陰法要の日程のお話でした。
最後までお付き合いくださり
ありがとうございます♪
次の記事「臍の緒の供養について」へ
関連記事「中陰飾りについて」へ